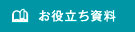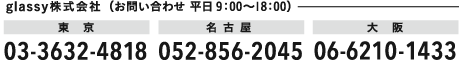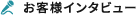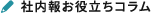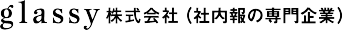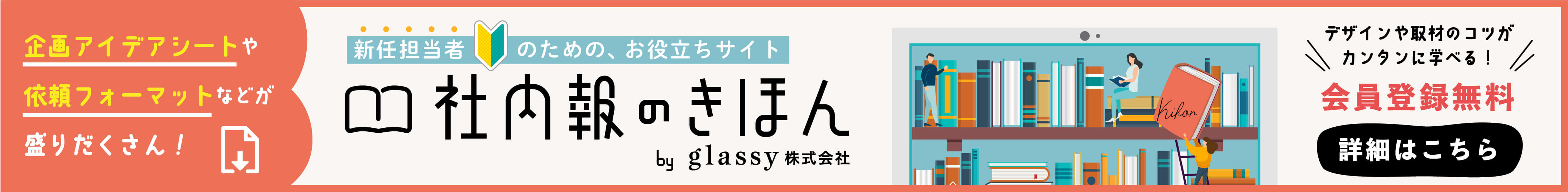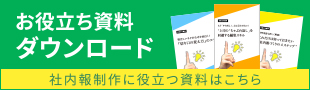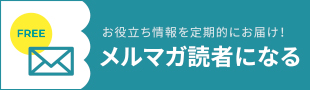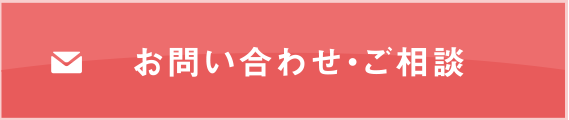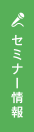社内報のつくりかた
知っているようで知らない漢字の使い分け
こんにちは、iisatoです。
前回は、間違えやすい同音異義語ついてお話ししました。今回は、読み方同じ!意味も同じ!でも、使うシーンがちょっと違う?そんな使い分けができたらカッコいい漢字についてお話します。
●「頂く」と「戴く」
「頂く」➤「頂」という漢字は「頭のてっぺん」や「いちばん高いところ」の意です。
「頂く」とは、「大切にする」、「敬って扱う」という意味があり、主に「人の行為」に対して使われます。例でいうと、「お客様にお越し頂く」、「時間を頂く」などです。
「戴く」➤「戴」という漢字は「頭の上にのせておく」の意です。「戴く」とは、「ありがたく受ける」という意味があり、主に「目に見える物をもらう」ときに使われます。例でいうと、「お土産を戴く」、「冠を戴く」などです。
「戴く」の方は、普段はなかなかお目にかかれない漢字ですよね。平仮名で「いただく」と書く例もよく見受けられます。ですが、調べてみると二つの漢字には上記のような使い方の違いがありました。
●「生かす」と「活かす」
「生かす」➤「生」という漢字は「生息」や「生活」などで使われるように生命にかかわることを表し、「生かす」とは「死なないようにする」という意味があります。例でいうと、「捕らえた虫を生かしておく」などです。
「活かす」➤「活」という漢字は「活動」や「活躍」などで使われるように勢いよく動くことを表し、「活かす」とは「有効に使う」という意味があります。例でいうと「経験を活かす」などです。
社内報を読んでいると、「生かす」と「活かす」はとてもよく出てきます。こちらも調べてみると、上記のような違いがありました。しかし、「活かす」の使い方は常用漢字に入ってはおらず、公用文などでは「生かす」の方を用いるようです。使い分けに迷ったときは、「生かす」を使うとよいでしょう。
以上、同じ意味でも実は使うシーンが異なる漢字をご紹介しました。上記は普段校正をしている際に、常々疑問に思っていたことです。それを調べることは、とても為になり知識も増えて面白いですね!まだまだたくさんご紹介します。皆さんの知識を増やすお手伝いができれば幸いです。
新着記事
2023.11.16
WEB社内報
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリットについて
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリット...
2023.10.11
WEB社内報
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも共感を生む方法
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも...
2022.01.05
社内報のつくりかた
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by glassy株式会社」
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by...
2021.12.15
WEB社内報
メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーションツールはどっち?
メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーショ...