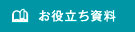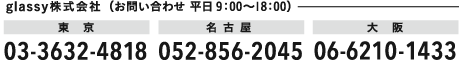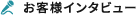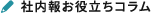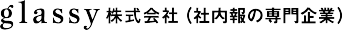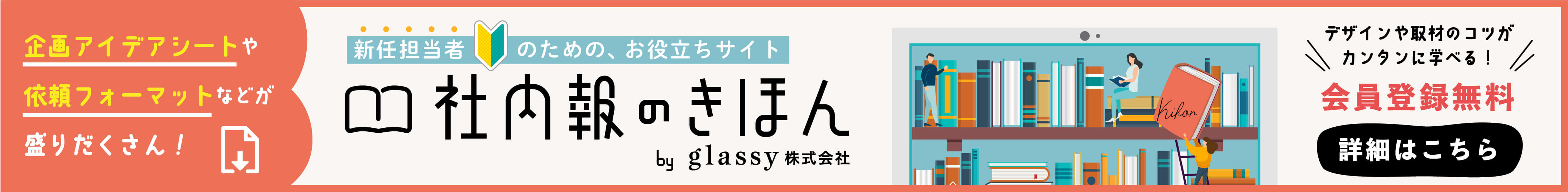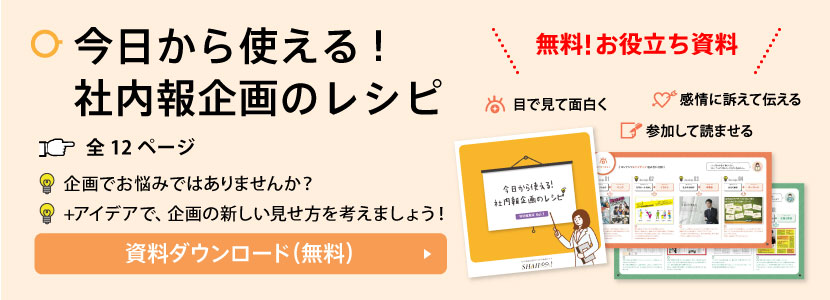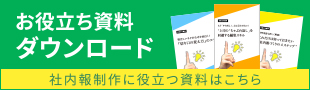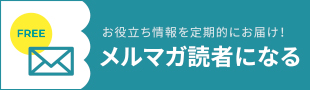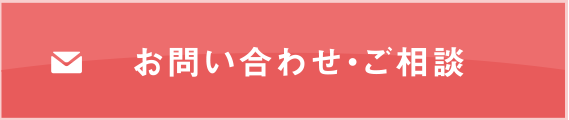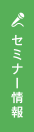社内報のつくりかた
【社内報撮影基礎】イベント撮影は「5W1H」が肝
目次
みなさん、こんにちはnemoです。
今回は新入社員も会社に慣れ始め、何かとイベントごとが多くなってくるこれからの時期に先駆け、しっかりとそのイベント状況を報告するために必要となる写真の撮り方について、ご紹介したいと思います。
まずはイベントの撮影、と言うところで、良く以下の項目が気を付けておくべき「基本の心得」と言われ、注意を払うべきポイントとされているのですが、簡単におさらいをしてみましょう。
イベント撮影の心得とは?
◯ イベントのプログラム(流れ)と実施位置を把握しておく
→次にどこで何が行われるか知っておかないと良い位置からの撮影ができません。
◯ イベント会場を事前にチェックしておく
→いわゆる「ロケハン」です。
当日の動線を含め、光の状態(明るさ)などもしっかりチェックしておきましょう!
◯ イベント会場の禁則事項を事前にチェックしておく
→当たり前ですが、会場内のルールはしっかりと守りましょう。
◯ イベントに参加している人の邪魔をしない
→カメラマンはあくまで裏方に徹します。
できる限り、楽しく過ごすみなさんに迷惑をかけないよう注意しましょう。
◯ 写真の仕上がりに自信がない場合はとにかく枚数を撮る
→悩むよりもまず行動!
撮影した中から後で良い写真をセレクトするようにしてみましょう。
◯ アクシデントが起こっても、うろたえない
→突然カメラのシャッターが切れなくなった…としても、落ち着いて行動を取りましょう。
いかがでしょう?
イベントの撮影をする際、上記項目を意識して現場に臨むことはできていましたでしょうか?
正直、初めてこの心得を耳にする方も多いのではないかと思いますが、一旦、上記に挙げた項目は頭に入れていただき、今度は以下の押さえておくべき写真の撮り方をインプットしていただければと思います。
今回のポイントは全部で6つ。
内容的に言えば、写真で[5W1H]を押さえる、というのが肝となります。
要は「いつ、どこで、何のために、誰が、どのように、何をした」を表すということですね。
ただただ記録写真を撮る、と言うよりも社内報ではそのイベントに参加できなかった方への報告を含め、当日の様子をできるだけ鮮度の高い状態で伝えるということが必要となってきますので、まずは話をするのと同様、写真だけでも説明ができるように、そのことを意識してカメラを構えるように心がけてみましょう。
イベント撮影6つの押さえポイント
[Point.1]When>日にちや時間帯が分かる写真
例として挙げると、写真のように外観を含めた開催の時間帯(外の明るさ)が分かるような写真、また日付記載のある案内板やプログラムなどを押さえた写真があると良いでしょう。
記事の中にも文章として組み込むことは出来ますが、写真ひとつで何時頃の開催だったのか、またいつ開かれたものなのかなど、そんな予備情報を見る側へすんなりと伝えることができます。
+アルファで会場の雰囲気なども一緒に押さえられると良いですね。
[Point.2]Where>会場内の様子が分かる全体写真
「どんな場所で開かれたのか」と言うことを、そのイベントに参加されたかった方々は案外気にされるものです。
会場全体の様子を人のいない開場前の状態、また開場後の人が入った状態、それぞれで押さえておくをおすすめします。
撮影の際は縦横の線の水平、垂直を意識して、シャッターを切るよう、ぜひ注意をしてみてください。
[Step.3]Why>何の(ために)イベントが開かれたのかが分かる写真
イベントを開くにあたっては、その「目的」が必ず存在するはずです。
開催報告を記事にする場合、何のために開かれたイベントなのか、その点も明確に表す必要がありますので、イベントのタイトル名やテーマなどが一目に分かる写真も押さえるように心がけておきましょう。
[Step.4]Who>重要人物(主役)の表情がわかる写真
開かれるイベントには必ず、その主役となる注目すべき人物がいるものです。 それは一人に限らず、複数だったりする場合もありますが、出来るだけその主役が誰なのかが見る側へ伝えられるよう、そしてその人物がはっきりと分かるよう、表情をしっかり捉えて撮影をするようにしましょう。
角度によって表情の見え方も変わるので、真横、斜め前、真正面…と、様々な方向からのバリエーション写真も合わせて押さえておきましょう。
[Point.5]How>イベント会場内の雰囲気を伝える写真
どんな雰囲気の中、イベントは開催されたのか、その様子をうまく伝えるためには、空間と人を押さえた写真、それぞれを撮影する必要があります。
空間は人までも含め、広い構図で撮影をし、人を押さえる場合は、動きのある様子を収めることがポイントとなります。
厳かな雰囲気の中で開かれるイベントでは、真剣に取り組むその表情を、フランクに楽しんで参加できるイベントでは、人と人との交流シーンや笑顔で話しているその瞬間を捉えられるよう、ファインダーを覗き込みながら、そのシャッターチャンスを待ち臨みましょう。
[Point.6]What>イベントで何が行われたかを表す写真

記事の中身もそうですが、イベント開催の報告を掲載するということは、イベントを開いたことで何が起こったのか、また結果としてどういったことが繰り広げられたのかなどを具体的に説明する必要があります。 そのため、イベントの進行に沿って、挨拶や発表、余興など、注目すべきものは全て押さえておくことが重要になります。
カメラマン自身も「イベントに参加したい!」という気持ちを持ってしまうところですが、そこは「ぐっ」と堪えて、撮るべきタイミングを見逃さないように、常に身の回りで起こることに意識を向けるように注力、またカメラを手放さないように注意しましょう。
イベント撮影は特に「洞察力」と「先読み」が必要にもなるのですが、まずは今回ご紹介させていただいた「5W1H」を忘れずに、カメラを構えるようにトライしてみてください。 撮影後、改めてデータを見返してみると「なんでこのタイミングでこのカットを撮影したんだろう?」や「もっと撮るべきものがあったんじゃないのかな?」などと、気になる点が見つけられたりもするのです。
「撮影したら終了」ではなく、「次はこんな写真を撮ってみよう!」と是非自分自身で課題を見つけ出すことにも調戦してみてくださいね。
撮りたいものが撮れるようになると、ますます撮影が楽しくなってきますよ!
Let’s Try!頑張りましょう。
新着記事
2023.11.16
WEB社内報
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリットについて
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリット...
2023.10.11
WEB社内報
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも共感を生む方法
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも...
2022.01.05
社内報のつくりかた
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by glassy株式会社」
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by...
2021.12.15
WEB社内報
メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーションツールはどっち?
メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーショ...