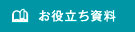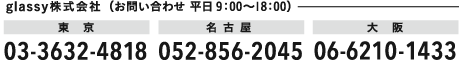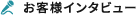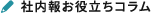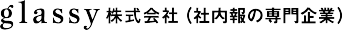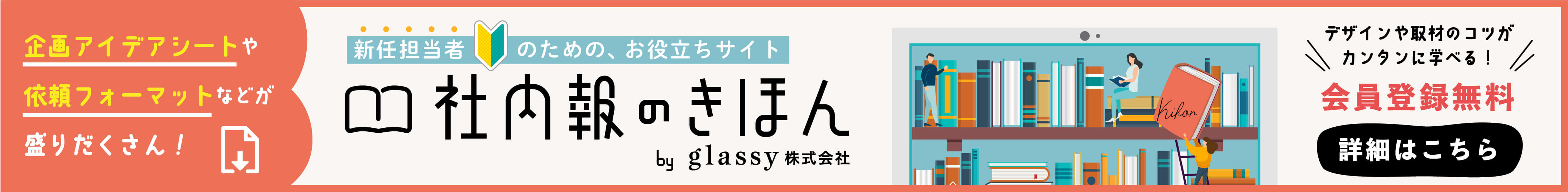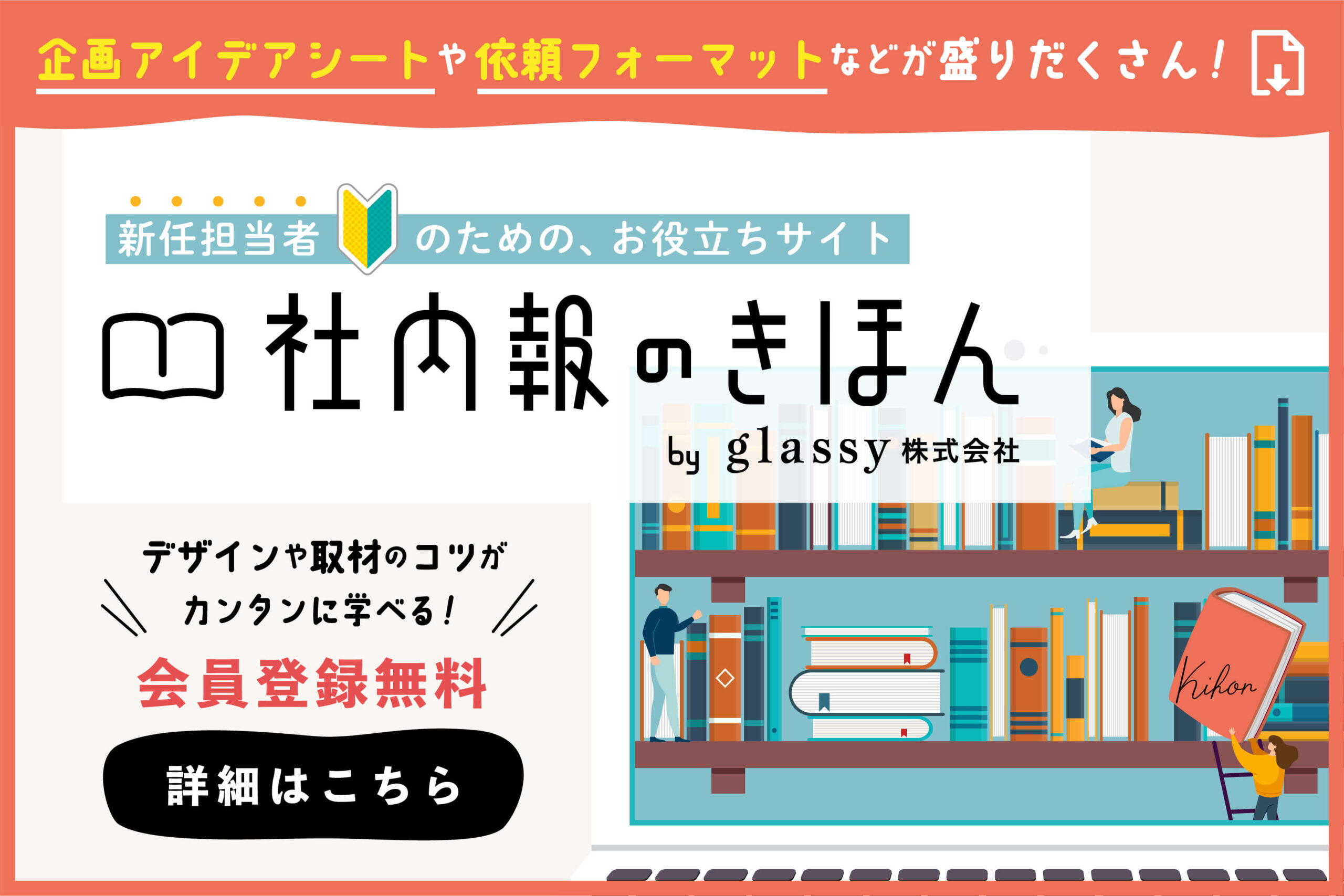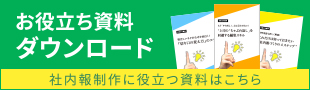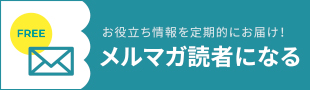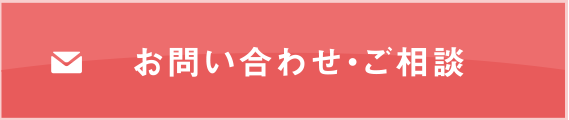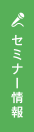WEB社内報
社内報のつくりかた
WEB社内報、いいね機能の落とし穴とは?
目次
SNSをはじめ、ビジネスシーンでも活用が広がっている「いいね機能」。
いいね機能は、手軽にポジティブな反応伝えられるよい機能ですが、落とし穴もあります。
そこで今回は、いいね機能の概要や、WEB社内報におけるいいね機能の落とし穴について詳しく解説します。
記事の後半では、WEB社内報サービスの導入時にいいね機能について検討すべきこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも「いいね機能」とは?
WEB社内報に限らず、SNSなどで「いいね機能」を目にしたことがある方や、実際に使ったことがある方は多いのではないでしょうか。
以下では、いいね機能の概要についてあらためてご説明します。
(1)今さら聞けない「いいね機能」とは
いいね機能は、FacebookやInstagram、TwitterなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を中心に実装されている機能です。
特定のコンテンツ(投稿)に対して、「楽しい」「面白い」「共感できる」「支持したい」などといった、好意的な反応を意思表示する際に使用されています。
いいね機能を押すことで、わざわざ文章(コメント)などで表現せずとも相手にポジティブな意思を伝えることが可能です。そのため、いいね機能は手軽なコミュニケーション手段の一つとして、双方向性を生むことのできる機能だといえます。
(2)Facebookで導入されたのが始まり
そもそもいいね機能は、SNSの一つ、Facebookで導入されたのが始まりです。
当時は、写真やコメント、広告などのコンテンツに「好き」という意思表示をする目的で開発されたといわれています。今ではFacebook社が運営するInstagramなどでも欠かせない機能となっているほか、ビジネスシーンでも、いいね機能がついた社内SNSやWEB社内報などが増えています。
WEB社内報におけるいいね機能の落とし穴
ビジネスでも活用される場面が増えつつあるいいね機能ですが、必ずしも良い面ばかりではありません。
以下では、いいね機能をうまく活用できない場合に陥りやすいパターンと、近年のSNSのいいね機能に対する動きについて解説します。
(1)うまく活用されなければ逆効果にもなる
いいね機能が実装されたWEB社内報サービスを導入した場合、発信されたコンテンツに対して、読み手は手軽にリアクションが取りやすくなります。一方で、いいね機能の活用方法次第では、逆効果ともなる恐れがあります。
陥りやすいパターンとして挙げられるのは、以下のような例です。
・いいね機能の利用層が固定化され、一部の読者のみにしか双方向性が生まれないパターン
・コンテンツへのいいね数が少なく、寒々しい印象になってしまうパターン
・いいね機能があることで、コメント率が低下してしまうパターン
・手軽な分、いいねをしなければならない空気感が生まれてしまうパターン
(2)メンタルには悪影響だと考える動きも
いいね機能は、いいねの数を気にしてしまったり、心理的なプレッシャーを抱えてしまったりして、メンタル面に不調を及ぼす可能性が指摘されています。
そのような背景を踏まえ、2021年5月には、FacebookとInstagramでいいね数を消すことのできる(表示/非表示の選択が可能になる)新機能が発表されました。
ただし、新機能導入前のテストでは、必ずしも全員がプレッシャーを軽減できるわけではなく、いいね数を非表示にすることを不便だと感じる人もいたことがわかっています。
このことから、いいね機能を一概に悪いものとするのではなく、メンタルには悪影響にもなる可能性があることを前提に、付き合い方をどのように工夫していくかを考えることが大切だといえます。
WEB社内報でのいいね機能との付き合い方
では、WEB社内報においては、いいね機能とどのように付き合っていけば良いのでしょうか。
以下では、WEB社内報サービスの導入時に、いいね機能について検討すべきことなどを解説します。
(1)WEB社内報サービス導入時に検討すべきこと
WEB社内報サービスを導入する際には、自社の企業風土がいいね機能の活用に向いているかどうかを検討することが重要です。例えば、いいね機能の実装された社内SNSなどを普段から積極的に活用しており、そのなかでいいね機能も理想どおりの使われ方をしているのなら、WEB社内報でもうまくいいね機能を活用できると期待されます。
一方で、先に述べた「陥りやすいパターン」が想定されるなら、いいね機能の活用には不向きかもしれません。
企業風土は一朝一夕ですぐに変えられるものではありませんから、無理にいいね機能を活用する方向に合わせるよりも、自社に合う方法を選択するのがベターです。
(2)いいね機能をON/OFFできるサービスを選ぶのが最適
とはいえ、実際に運用してみないと、いいね機能をうまく活用できるかどうかわからないという方もいるかと思います。そこでおすすめなのが、いいね機能をON/OFFで切り替えられるWEB社内報サービスを選ぶことです。
glassy株式会社の提供するWEB社内報クラウドシステムWEB社内報「WMZ」では、管理者側でいいね機能のON/OFFの設定が可能です。まずは、機能ONの状態で運用を始めてみて、自社の風土には合わないと感じたらOFFに切り替えるなどと柔軟に対応できるため、WEB社内報の運用を失敗しにくくなります。
*コメント機能のON/OFFの設定も可能です。
おわりに
WEB社内報のいいね機能は、本来、コンテンツの発信者と読み手との双方向性を生むことのできる素晴らしい機能です。
しかし、いいね機能自体が企業風土に合わない場合や、うまく活用できない場合は、逆効果となってしまう可能性もあります。
そのため、企業風土に合わせて、いいね機能を利用する・しないを選択することをおすすめします。特に、実際に機能を活用してみてから柔軟に対応したい企業には、いいね機能を管理者側でON/OFFできるWEB社内報「WMZ」が最適です。
WEB社内報「WMZ」では、いいね機能以外にも、企業風土に合わせてさまざまな機能をカスタマイズすることができます。
WEB社内報サービスの導入を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
新着記事
2023.11.16
WEB社内報
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリットについて
Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリット...
2023.10.11
WEB社内報
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも共感を生む方法
社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも...
2023.09.13
WEB社内報
WEB社内報ツールおすすめ5選!導入のメリットと選び方を紹介
WEB社内報ツールおすすめ5選!導入のメリットと選び方を...
2022.01.05
社内報のつくりかた
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by glassy株式会社」
無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by...