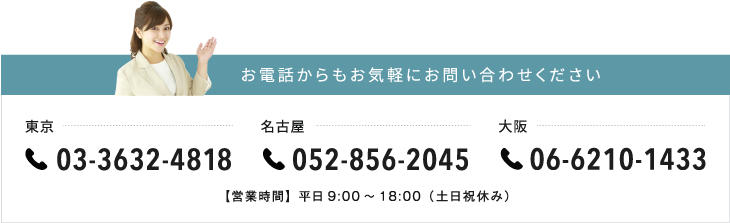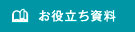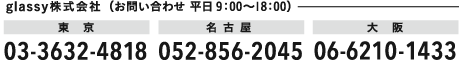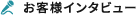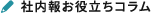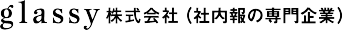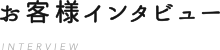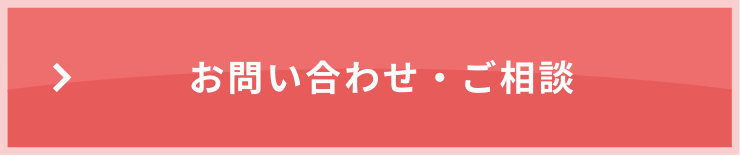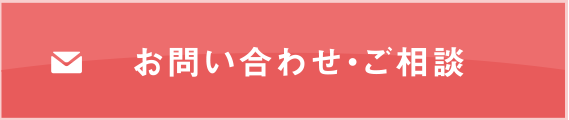広報担当者の取り組みと、プロの視点との連携で
もっと「伝わる広報誌」へ。
広報担当者の取り組みと、プロの視点との連携で
もっと「伝わる広報誌」へ。

大光電機株式会社
経営戦略室
津留 章 さん(右)
尾上 姫子 さん(左)
木下 莉彩 さん(中)
-
※所属・肩書はインタビュー当時のものです。
-
抱えていた課題
・より広いターゲットに伝わる冊子にリニューアルする必要があった
・照明を手がける企業としてビジュアルに訴える誌面にしたかった
glassyを選んだ理由
・プレゼンテーションの内容に納得
・デザイン力の高さ
・訪問した際に感じた社風も好印象
広報誌を発行した効果
・全国の社員のコミュニケーション向上
・社員のエンゲージメントにも好影響
・ビジュアルに訴える内容で営業ツールとしても機能
-
長く続いた広報誌の位置づけを見直すことからスタート
-
―まず、御社が広報誌「DAIKO WAY」で発信を始められた経緯をお聞かせください。
津留さん
大光電機は創業以来、照明器具のデザインから製造・販売までを一貫して手がけています 。照明の種類は多岐に渡り、その魅力も奥が深いためお客様へいかに発信するかが課題でした。そこで20年以上前から、社内でまとめた情報をコピーして配布する活動をしていました。 -
尾上さん
最初は時事ネタや豆知識などを盛り込んで、仕事の合間に息抜きになるような内容をお客さまにお届けする感じだったそうです。 -
津留さん
ずっと社内で手づくりしていたのですが、その後、より体裁を整えた冊子へのニーズが高まり社外に依頼することになりました。誌名の「DAIKO WAY」が生まれたのもそのときです。 -

-
―長く続けられてきた冊子のリニューアルを決断されたのはなぜですか。
尾上さん
きっかけは4年ほど前の社長交代です。新社長から「印刷物、発行物をもっと良くしよう」という方針が打ち出され、広報誌もその一環として「もっとお客さまに製品の魅力が伝わるものに」と見直しをしました。創刊から15年以上続くなか、ここ10年間ほどはデザインもコンテンツも変化がなく、マンネリ化していたことも背景にありました。 -
―見直しに当たっては、どのような課題をピックアップされましたか。
尾上さん
従来の「DAIKO WAY」は、どちらかというと企業トップの方に向けたブランディングツールでした。でも今後は、現場の実務担当者や若手社員にも届くような、もっと広く親しんでもらえる情報誌にしたいという思いがありました。当社は、世間で話題になるようなホテルや商業施設などたくさんの物件に関わらせていただいております。せっかくそういう魅力的な物件や照明演出を手がけているのに、それを十分に伝えられていないという課題感がありました。 -
津留さん
もちろん今までも、そうした物件の紹介はしてはいたのですが、文字ベースの構成になっていたので、照明のデザインの魅力や可能性の広がりなども、もっとビジュアルを中心としたかたちで表現できたらいいなと思っていました。 -
決め手は社風、人柄、コストと作業負担の軽減
-
―パートナーとしてglassyを選んでいただいた理由を教えてください。
津留さん
広報誌の制作会社をウェブで数社ピックアップした中の一つにglassyさんがありました。ちょうどそのころ開催していたインテックス大阪の展示会で、glassyさんが出展されているのを知って、せっかくですので直接お話しをうかがいました。対応いただいた担当者の方の説明が丁寧でわかりやすく、好印象でした。その後、東京で打ち合わせをした際も、いろいろな企業の事例などを共有いただいて、当社のやりたいことを叶えてくれるという手応えを得ました。 -
尾上さん
プレゼンテーションの中にあった「社内の魅力を発信し続けることで、それが社外にもにじみ出ていく」という言葉が強く印象に残っています。当社の「DAIKO WAY」は基本的に社外向けの広報誌ですが、インナーブランディングに向き合っている会社さんであれば、良い提案をしてくださるのではないかと期待しました。 -
木下さん
社員の方の人柄に魅了されました。
例えば、実際にオフィスに伺った時、みなさんが立ち上がって挨拶してくださり、私たちの会社もそういった風土があり、共通点があるなと感じました。あと、フランクな方が多い印象です。 -

*広報担当者の尾上さん(左)、木下さん(右)
-
―他の制作会社との比較などもされたのでしょうか。
尾上さん
何社か見積もりも取りましたが、価格が合わなかったり、内容が期待と違ったりするところもあって。その中でglassyさんは価格・内容ともにバランスが良く、「ここにお願いしたい」と社内でも意見が一致したんです。 -
津留さん
もう一つ大きな決め手となったのが、制作だけでなく発送まで一括でお願いできるという点でした。以前は納品された冊子を別の配送会社様で仕分けから発送まで行っていたので、手間も費用もかかっていましたが、リニューアル後は実際にコストも削減できました。 -
一新した誌面で、社員のエンゲージメントも向上
-
―リニューアル後、どのような効果がありましたか。
津留さん
照明という商材は独特というか、その魅力を、私たちもなかなかglassyさんに伝えきれていなかった部分もあって、そこのすり合わせが最初は難しかったところですが、号を重ねるごとにブラッシュアップされて、いまは「魅せる広報誌」になったと実感しています。 -
尾上さん
お客さまからもデザインを高く評価していただいています。広報担当者も自分で取材をしてテキストを起こすことで、商材への理解が深まったことも効果の一つかもしれません。それを最後にデザインで綺麗に整えて出してくださるので、とても助かっています。 -

*リニューアルされた大光電機 広報誌「DAIKO WAY」
-
―社員の皆さまの反応はどうですか。
尾上さん
例えば、東京のメンバーが手がけた案件について、別の地域の社員が「こんなプロジェクトがあったんだ」という声が上がって、社員のエンゲージメントも高まりました。地方の拠点にいる社員たちにとっても、自分たちの会社が関わっているプロジェクトを知る良い機会になったと思います。 -
木下さん
紙面には、社員紹介のコーナーもあって私が担当しているのですが、どのように自分たちの部署を魅力的にアピールしようかと、さまざまな提案をしてきたりと、みんなも楽しんで参加してくれているのを感じています。 -
尾上さん
部単位にしたことで、みんな割とノリノリで撮影やコメント作成に臨んでくれていますね。そこで会話が生まれたりするのも効果の1つと言えます。 -

-
木下さん
社内の部署に掲載の依頼をすることを通じて、私自身も社内のいろいろな人とつながりができました。直接お会いできた時に会話のきっかけができるのもうれしいですね。 -
津留さん
特集で取り上げた商材を、狙ったお客さまに事例としてお渡しできるのもメリットです。営業ツールとしても役立っています。 -
尾上さん
そうですね。新規のお客さまを訪問する際には、社風を伝えるという意味もあって、会社案内と一緒に営業さんがバックナンバーを持って行っているようです。メールでは埋もれてしまう情報も、紙媒体なら、仕事の合間に手にとっていただけると期待しています。 -
毎月の発刊は大変ながら「継続」することが重要
-
―これからの「DAIKO WAY」の展望をおしえてください?
津留さん
まずは「継続すること」です(笑)他社さんでも、がんばって始めたものの、あとが続かないケースもあると思います。実際、当社でも、立ち上がったコンテンツが自然消滅してしまった例は少なくないので、まずは「必ず続ける」こと。もちろん中身はどんどん見直して、お客さまに伝えたいことがちゃんと伝わるように工夫したいです。そういう意識を持って取り組んでいけば、自然と良いものになっていくと思います。 -
木下さん
とにかく地道に、ですね。 -
いい連携による広報誌づくりをこれからも
-
―最後に、制作パートナーである弊社への期待を教えてください。
尾上さん
良い企画のご提案をいただきつつ、記事については社員目線に立って作っているところが、当社の特徴だと思うのですが、中身は自社で詰めて、そこをデザイナーの方に綺麗に整えてもらうという、いい感じの連携ができているので、引き続きよろしくお願いします。 -
津留さん
glassyさんのチームの雰囲気や人柄にも助けられました。今後もそのスタンスで、私たちの思いに寄り添ってもらえればと思います。 -
―貴重なお話をたくさん伺うことができました。ありがとうございました。
ひと言メッセージ

ひと言メッセージ
尾上さん(右) いつも時間のない中で柔軟に対応していただいて感謝しています。
木下さん(中) 紙面レイアウトの提案にも助けられています。ありがとうございます。